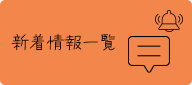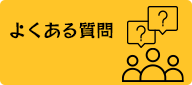国民健康保険税について
国民健康保険税の決め方
国民健康保険税は、医療保険給付に充てる「医療分」、後期高齢者医療制度への支援に充てる「後期高齢者支援金分」、介護納付金に充てる「介護分」の合算で算定されます。
医療分、後期高齢者支援金分はすべての国保加入者について課税されます。介護分については、40歳以上65歳未満の国保加入者について課税されます。
令和7年度国民健康保険税
|
|
医療分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護分 (40~64歳) |
|---|---|---|---|
|
所得割 |
6.4% |
2.2% |
2.2% |
|
資産割 |
10% |
ー |
ー |
|
均等割 |
33,000円 |
14,000円 |
12,000円 |
|
平等割 |
3,000円(注1) |
ー |
ー |
|
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
<計算の方法>
- 所得割 課税標準額(注2)×税率
- 資産割 固定資産税額(土地・家屋にかかる分)×税率
- 均等割 国保加入者の人数(介護分は、40歳以上65歳未満の国保加入者の人数)×一人当たりの税額
- 平等割 1世帯当たりの税額
(注1)国保に加入している人が後期高齢者医療制度に移行した結果、世帯内の被保険者が1人だけとなる世帯は、5年間「特定世帯」として平等割が2分の1軽減されます。5年経過後は、3年間「特定継続世帯」として平等割が4分の1軽減されます。軽減後の医療分平等割額は特定世帯では1,500円、特定継続世帯では2,250円となります。
(注2)課税標準額とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から国民健康保険税の基礎控除額43万円を控除した後の額です。
納税義務者
国民健康保険税は、世帯主本人が国民健康保険の被保険者でない場合であっても、擬制世帯主としてその世帯主に国民健康保険税が課税されます。
年度の途中で国保の加入状況に変更があった場合
年度の途中で加入・脱退した場合
- 国保に加入した:加入した月分からの保険税を納めます
- 国保を脱退した:脱退した月の前月分までの保険税を納めます。
年度の途中で国保加入者が40歳、65歳、75歳になる場合
- 年齢が40歳に到達した:40歳に到達した月から介護分を納めます。(納税通知書が届いている場合には、変更通知書が届きます。)
- 年齢が65歳に到達した:65歳に到達する前月分まで介護分を納めます。(予め到達月以降の介護分を減額して課税しているため、変更通知書は届きません。)
- 年齢が75歳に到達した:75歳に到達する前月分まで国民健康保険税を納めます。(予め到達月以降の国民健康保険税を減額して課税しているため、変更通知書は届きません。)
国民健康保険税の試算について
国民健康保険税の試算を希望される方は、下記のものを確認のうえ、窓口またはお電話にてお問い合わせください。
- 加入する人数と加入者の年齢
- 世帯主及び加入する人の収入状況の分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
- 加入する人の固定資産税の課税額の分かるもの(固定資産税の納税通知書等)
国民健康保険税概算早見表
国民健康保険税の概算早見表では、単身世帯の方のおおよその国民健康保険税額を確認することができます。ご自身の前年の収入のわかるものをご用意いただいたうえでご確認ください。
(注意)早見表は、概算の国民健康保険税です。実際の税額とは異なる場合がありますので、目安としてご利用ください。
納付方法
普通徴収
令和5年度より、原則口座振替での納付をお願いしております。
(口座振替を強制するものではありません。口座振替が困難な場合は、納付書での納付も可能です)
納期は最大8回です。(加入のお届け日によって回数が変わります。)
特別徴収
年金天引きによる納付方法です。
年金天引きから口座振替への変更を希望される場合は、申請が必要となります。
申請に必要なもの
今まで国民健康保険税を口座振替以外の方法により納付していた方
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 預貯金通帳
- 預貯金通帳の届出印
※医療保険課で申請後、速やかに金融機関に口座振替依頼書の提出をしていただきます。
なお、一部金融機関であれば、市役所窓口にて口座振替の申し込みができます。
今まで国民健康保険税を口座振替の方法により納付していた方
- 国民健康保険税口座振替通知書
- 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
※なお、支払った国民健康保険税で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
特別徴収(年金天引き)の場合は年金受給者、普通徴収(口座振替)の場合は口座名義人の控除となります。
国民健康保険の軽減制度と減免制度
低所得者に対する均等割額及び平等割額の軽減
一定所得以下の世帯には、保険税の軽減制度があります
前年中の世帯の軽減判定所得(注1)が基準額以下の場合には、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
(注1)「軽減判定所得」とは、世帯の被保険者(擬制世帯主及び特定同一世帯所属者(注2)を含む。)の「総所得金額及び山林所得金額等」の合算額ですが、以下の注意点があります。
- 青色専従者給与額及び事業専従者控除額は経費に算入されず又は控除されません。
- 事業専従者の給与所得はないものとして扱います。
- 土地・建物の譲渡所得は、特別控除が適用されません。
- 前年12月31日現在で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得から15万円が控除されます。
(注2)「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、引き続き今までの世帯に属する人をいいます。
| 基準額 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注3)―1) | 7割 |
|
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) +30.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 |
5割 (7割軽減世帯を除く) |
|
43万円+10万円×(給与所得者等の数―1) +56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数 |
2割 (7割・5割軽減世帯を除く) |
(注3)「給与所得者等の数」とは、納税義務者、被保険者または特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数をいいます。
未就学児に対する均等割額の軽減
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の5割を軽減します。ただし、低所得者世帯に対する軽減を受ける方は軽減後の均等割額より減額します。
出産被保険者に係る産前産後期間の保険税軽減
出産された被保険者を対象に、所得割・均等割の4ヶ月分(多胎出産の方は6ヶ月分)を軽減します。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)。
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
軽減方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます 。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
必要書類
届書
母子健康手帳など出産予定日(又は出産日)の分かる書類
減免制度
納税義務者又は生計を主として維持する人が震災、風水害、火災などの災害により住宅等の財産に著しい損害を受けたり、疾病等により著しく生活が困難になった場合には、納期限までにご相談ください。減免又は納期限の延長を受けられる場合があります。
住民税の申告をお願いします
国民健康保険税は、前年の申告の内容により、国民健康保険税の算定や軽減判定を行っておりますので、加入者の方は、所得の有無にかかわらず住民税の申告をしてください。(年末調整済みの方や確定申告済みの方は除く)
世帯主の申告書上、被扶養者として申告をされている場合であっても、国保に加入されている方は、本人名義による申告が必要です。
後期高齢者医療制度に伴う緩和措置
特定同一世帯所属者の属する世帯に係る減額措置
- 特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行した人で、引き続き今までの世帯に属する人)が属する世帯は、均等割額及び平等割額の軽減の判定を従前と同様に行います。
- 特定同一世帯所属者が属する世帯の国民健康保険加入者が1人になった場合、特定世帯として5年間平等割が2分の1軽減されます。また、特定世帯となってから5年間経過後、8年目までの間の世帯は、特定継続世帯として平等割が4分の1軽減されます。
社会保険等の旧被扶養者に係る減免措置
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者が国民健康保険に加入し、かつ65歳以上の場合には次のとおりとなります。
- 被扶養者の所得割額と資産割額が免除されます。
- 該当してから2年間の均等割額が2分の1となります。
- 被保険者がその被扶養者1人の場合には、該当してから2年間の平等割額が2分の1となります。
*他の制度による軽減の額が上記を上回る場合は適用されません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7712
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク