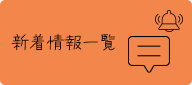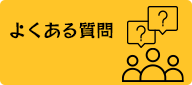高額療養費/高額医療高額介護合算制度/食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
高額療養費
1か月の医療費の一部負担額が以下の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。
該当者には、案内及び申請書が届きますので案内に従い、申請してください。
なお、一度申請されますと次回からは、該当した診療月の3か月後の下旬以降に、ご指定いただいた口座に自動的に振り込みいたします。
自己負担限度額(1か月)
| 所得区分 | 外来の場合(個人ごとに計算) の診療月ごとの自己負担限度額 | 入院と外来があった場合(世帯単位で計算)の診療月ごとの自己負担限度額 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数回該当 140,100円] |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[多数回該当 140,100円] |
| 現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数回該当 93,000円] |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[多数回該当 93,000円] |
| 現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数回該当 44,400円] |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[多数回該当 44,400円] |
| 一般(一定以上所得含む) | 18,000円(8月~翌年7月までの年間上限額144,000円) | 57,600円[多数回該当 44,400円] |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※多数回該当:過去12か月に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当
※所得区分について
- 現役並み所得者3:課税所得690万円以上の方
- 現役並み所得者2:課税所得380万円以上690万円未満の方
- 現役並み所得者1:課税所得145万円以上380万円未満の方
- 一般(一定以上所得含む):現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2に該当しない方
- 低所得者2:同一世帯の全員が、住民税非課税の方
- 低所得者1:同一世帯の全員が、住民税非課税かつ所得が0円(年金収入の場合は控除額を80万6,700円で計算)の方
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同一世帯の被保険者の所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を引いた金額が210万円以下の場合、区分は「一般」となります。
※下記の条件のいずれかに該当する場合は、申請により区分は「一般」となります。
- 同じ世帯に被保険者が1人の場合
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満) - 同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計が520万円未満
※所得区分が「一般」の方のうち、一定以上の所得のある方(2割負担の方)については、負担を抑える配慮措置があります。
詳細は次のページをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定
マイナ保険証を利用すること、もしくは「限度区分を併記した資格確認書」を医療機関等に提示することで、同じ月で同じ医療機関での窓口負担の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。マイナ保険証をお持ちでない方の限度額適用・標準負担額減額認定については申請が必要です。
詳細は次のページをご覧ください。
75歳到達月の自己負担限度額
75歳の誕生日を迎えると、健康保険は自動的に後期高齢者医療に切り替わるため、75歳の誕生日の属する月(75歳到達月)の高額療養費は、誕生日前の健康保険と後期高齢者医療の2つの制度からそれぞれ算定されることになります。そのため、通常月と比べて負担が増えることのないように、75歳到達月の自己負担限度額は、通常の2分の1の額で計算されます(1日生まれの方は除きます)。
高額医療・高額介護合算制度
1年間に払った医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
該当者には、毎年1月以降に案内及び申請書が届きますので案内に従い、申請してください。
| 期間:8月~翌年7月 | 医療保険と介護保険の自己負担額の合算後の限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
※介護保険のサービスを利用していない世帯は、制度の対象とはなりません。
※対象期間内に、埼玉県外から転入された方等は、以前加入していた保険での自己負担額を蕨市では把握できないため、案内の通知が届かない場合があります。
入院時の食事などにかかる自己負担額(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)
入院時の食費・居住費の自己負担額は下表のとおりです。
一般病床に入院した場合は食事療養標準負担額(食費のみ)を、療養病床に入院した場合は生活療養標準負担額(食費+居住費)を負担します。
マイナ保険証をお持ちでない方で低所得者1・低所得者2に該当の方が入院される際は、「限度区分を併記した資格確認書」が必要です。
マイナ保険証もしくは「限度区分を併記した資格確認書」を提出しなかった場合は、一般の所得区分の負担額となります。
※「限度区分を併記した資格確認書」については次のページをご覧ください。
(令和7年4月から)
| 区分 | 食事療養標準負担額(1食) |
|---|---|
|
現役並み所得者 一般(下記以外の人) |
510円*1 |
| 低所得者2 | 240円(190円*2) |
| 低所得者1 | 110円 |
マイナ保険証の利用で、申請なく食事代が減額されます。ただし、長期入院該当※2の場合は別途申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちでなく、低所得者1・2の人は医療保険課にて申請いただくと、資格確認書に限度額区分を併記します。併記した資格確認書を医療機関で提示することで、食事代が減額されます。
※1…指定難病患者は300円。
※2…長期入院該当(過去12か月に入院日数が90日超)の場合は、食事代がさらに減額されます。入院日数の分かる領収書などを添えて再度申請してください。なお、長期入院該当日は、届出月の翌月1日となります。
| 区分 | 医療の必要性の低い方:食費 (1食) | 医療の必要性の低い方:居住費(1日) | 医療の必要性の高い方:食費 | 医療の必要性の高い方:居住費 | 医療の必要性の高い方(指定難病患者):食費 | 医療の必要性の高い方(指定難病患者):居住費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 一般 |
510円 (470円*3) |
370円 |
510円 (470円*3) |
370円 | 300円 | 0円 |
| 低所得者2 |
240円 |
370円 |
240円 (190円*2) |
370円 |
240円 (190円*3) |
0円 |
| 低所得者1 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
※3…管理栄養士等により栄養管理が行われているなどの要件を満たさない場合。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課長寿医療係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7503
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク