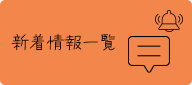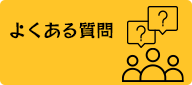障害者差別解消法について
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは
すべての人が障害のあるなしで分け隔てられることなく、お互いの人格や個性を認め合いながら共生する社会の実現を目指して障害者差別解消法は制定されました。
この法律は、国や都道府県、市区町村といった行政機関等や会社やお店などの事業者に対し、障害のある人への「不当な差別的取扱い」を禁止しています。また、障害のある人から申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で「合理的配慮の提供」を義務づけています。
「不当な差別的取扱い」とは
「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して「正当な理由※」がなく「障害がある」という理由だけで、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供する場所・時間帯などを制限したりといった「障害のない人と異なる取扱い」をすることで、障害のある人の権利や利益の侵害をするものとして禁止されています。
※正当な理由:客観的に見て正当な目的のもとに行われ、目的に照らしてやむを得ないといえる場合。
「合理的配慮の提供」とは
合理的配慮の提供とは、障害のある人の活動などを制限する社会的障壁を取り除くために、何らかの対応を求める「意思の表明」があったとき、その実施が「過重な負担」とならない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行うことです。国の行政機関や地方公共団体などと同様に、事業者にも提供が義務付けられています。
不当な差別的取扱いに当たり得る例(例示であり、これに限られるものではありません)
正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。
【例】
- レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを理由に断られた
- 障害を理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた
合理的配慮の不提供に当たり得る例(例示であり、これに限られるものではありません)
障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「※ 社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
【例】
- 災害時の避難所で聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった
- 会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった
※社会的障壁とは? 障害者にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障害のある人への偏見など)
【例】
- 道路の段差・・・3cm程度の段差でも車いすは進めなくなります
- 書類・・・難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
蕨市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の制定について
平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、蕨市職員による取組を確実なものとするため、「蕨市障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定しましたので、同法第10条第3項に基づき公表します。
障害者差別解消法に関する相談窓口
障害のある方、その家族及びその他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止又は解決を図るための相談は、福祉総務課障害者福祉係(048-433-7754)において受け付けています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク