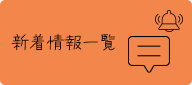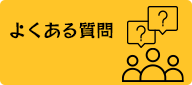色々な感染症【感染症情報】
蚊を介する感染症の予防対策 ~感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を~
感染症流行地域では、蚊に刺されないようにしましょう。
・海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状況を把握しましょう。もし蚊を媒介とする感染症の流行地域へ渡航される場合には、蚊に刺されないように万全な対策をしましょう。
・屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されない対策をしましょう。
住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしましょう。
・蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生するので、日頃から住まいの周囲の水たまりを無くすように心がけましょう。
※ 蚊の活動は概ね10月下旬頃で終息します。これらの対策は10月下旬頃までを目安に行いましょう。
水痘の流行注意報が発令されました。
埼玉県感染症発生動向調査による県内医療機関(定点)からの水痘の報告数は4月初旬から増加し、第 19 週(令和 7 年 5 月 5 日から 5 月 11 日まで)は1定点当たり 1.43 人と、国の定める注意報の基準値である1人を大きく上回り、増加傾向が確認されました。
水痘は、いわゆる「みずぼうそう」のことで、かゆみを伴う全身性の発疹や発熱が現れる感染症です。感染力が強く、接触感染・飛沫感染・空気感染のいずれでも広がります。妊婦など重症化しやすい方は、特に注意が必要です。感染が疑われるときは、事前に連絡した上で、速やかに医療機関を受診するととともに、家庭では、タオルや食器等の共用を避けるほか、マスク・手指衛生の徹底、換気などの対策に努めましょう。
水痘の予防のポイント
スケジュールに沿ったワクチン接種
1・2歳のお子さんは水痘ワクチンの定期予防接種の対象です。予防接種
スケジュールに沿って接種を受けましょう。
マスクの着用等普段からの咳エチケットの励行
飛沫感染を防ぐため、普段からマスクの着用等咳エチケット((1)咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと、(2)マスクをしない状態で咳やくしゃみが出るときはハンカチなどで口を覆うこと、(3)手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗うこと等)を守ることを心掛けましょう。
患者が使用したもの等に触れた後の手洗い
接触感染を防ぐには、手指などに付いたウイルスを流水・石けんによる手洗いで物理的に取り除くことが有効です。患者の水疱や患者が使用したものに触れた後は、傷口や鼻や口、目などの粘膜に触れる前に必ず手を洗いましょう。
水痘が疑われる場合は
周りへの感染に気を付けましょう。症状によっては、早めに事前に連絡の上、医療機関を受診しましょう。なお、治療には抗ウイルス薬が使用されるほか、かゆみなどの症状に応じた対症療法が行われます。
関連情報
伝染性紅斑の流行警報が発令されました
伝染性紅斑の増加に伴う注意喚起について、令和7年4月 30 日に公表された4月 14 日から 20 日までの1週間における定点医療機関(※)からの報告数は過去 10 年間の最高値まで増加しております。
伝染性紅斑は特徴的な発疹が現れる前に感染が広がりやすいので、普段から咳エチケット、手洗いなどの対策を心がけ、感染予防に努めましょう。
麻しん(はしか)の流行について
麻しん(はしか)の感染拡大
麻しんについては、現在、海外における流行が報告されています。日本国内においても、海外からの輸入症例を契機とした国内における感染伝播事例が報告されています。今後、更なる輸入症例や国内における感染事例が増加する可能性がありますので、ご注意ください。
感染経路・症状
麻しん(はしか)は、麻しんウイルスによって引き起こされる病気で、空気感染、飛沫感染、接触感染で人から人に感染が伝播します。感染すると、10日から12日の潜伏期間を経て、38℃程度の発熱、風邪のような症状(咳や鼻水など)が現れ、2~4日間続きます。口の中に小さな白い発疹の後に高熱(多くは39.5℃以上)となり、体中に赤い発疹が現れます。
麻しんが疑われる場合
発熱、発疹など麻しんに特徴的な症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話等で連絡の上、医療機関の指示に従って受診してください。その際、症状出現日の10日から12日前(感染したと推定される日)の行動(海外の滞在歴や人が多く集まる場所へ行ったかどうか等)について、医療機関にお伝えください。
また、麻しんの感染力は非常に強いと言われています。医療機関へ移動される際は、周囲の方への感染を防ぐためにもマスクを着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。
予防するためにできること
麻しんは感染力が強く、空気感染もするため、手洗い・マスクだけでは十分に予防できません。麻しんの予防接種が最も有効な予防法といえます。
麻しんの定期予防接種について
MR(麻しん、風しん)混合ワクチンを接種します。効果を高めるために、2回の接種が必要です。
第1期:1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで
第2期:小学校就学前の1年間
新型コロナウイルス感染症の流行により規定の接種時期に定期接種を受けることができなかった方は、下記をご確認ください。
定期予防接種対象以外の方について
「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことがない方」は、お近くの医療機関や、かかりつけ医にご相談ください。
なお、麻しん含有のワクチン(MRワクチン、麻しんワクチン)の接種歴は母子健康手帳や接種証明書でご確認ください。
関連情報
帯状疱疹について
帯状疱疹とは
水痘(みずぼうそう)と同じウイルスが原因で起こる皮膚疾患です。水痘が治癒した後もウイルスが神経に潜伏し、免疫低下や加齢に伴い、ウイルスが再び活性化することによって発症します。
症状
皮膚症状の特徴として、皮膚に分布している神経に沿って、水疱が帯状に出現します。
通常、皮膚症状の出現2~3日前から痒み、もしくは痛みが出現し、初期は皮膚が赤く腫れます。1週間程度経過すると、水疱が多発するようになり、発熱、頭痛、リンパ節腫脹などの症状も出現するようになります。
通常2~4週間で水疱が破れて痂皮化(かさぶたになる)し、皮膚症状が正常に戻ります。
合併症
最も一般的な合併症は、帯状疱疹後神経痛と呼ばれる長期の神経痛です。
この神経痛は3か月以上続く疼痛で、帯状疱疹患者の10~50%に出現し、高齢になるほど多くみられます。
治療
抗ウイルス薬の投与を行います。より早期に使用すると効果が高く、重症例では入院して点滴治療を行います。
予防のポイント
免疫力が低下しないように、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど日頃から体調管理に努めることが大切です。
ワクチンについて
帯状疱疹は、ワクチンを接種することで発症や重症化を抑えることができます。
帯状疱疹のワクチンは、50歳以上の方が対象です。接種をご希望の方は、医療機関(内科、皮膚科等)へ直接ご相談ください。
帯状疱疹は法令で定められた定期予防接種の対象疾患でないため、ワクチンを接種する場合は任意予防接種となります。
蕨市では令和6年4月1日から帯状疱疹予防接種費用助成金交付事業を開始しました。下記のページをご覧ください。
RSウイルス感染症について
RSウイルス感染症とは
RSウイルスの感染による呼吸器の感染症です。生涯の間に何度も感染と発病を繰り返しますが、生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の児がRSウイルスに少なくとも1度は感染するとされています。
感染経路
RSウイルスは主に接触感染と飛沫感染で感染が広がります。RSウイルスは、麻疹ウイルスや水痘ウイルスの感染経路である空気感染はしないと考えられています。
症状
- 通常RSウイルスに感染してから2~8日、典型的には4~6日間の潜伏期間を経て発熱、鼻汁などの症状が数日続きます。多くは軽症で自然軽快しますがが、重くなる場合には、ひどい咳、喘鳴、呼吸困難などの症状が出現し、場合によっては、細気管支炎、肺炎へと進展します。
- 初感染乳幼児の約7割は、鼻汁などの上気道炎症状のみで数日のうちに軽快しますが、約3割では咳が悪化し、喘鳴、呼吸困難などが出現します。重篤な合併症として注意すべきものには、無呼吸発作、急性脳症等があります。
- 成人では通常は感冒様症状のみですが、RSウイルスに感染した小児を看護する保護者や医療スタッフでは、一度に大量のウイルスに曝露して感染することによって、症状が重くなる場合があります。
- RSウイルスは特に慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者において急性の重症肺炎を起こす原因となることが知られています。
治療
RSウイルス感染症には特効薬はありません。治療は基本的には対症療法(酸素投与、点滴、呼吸管理など症状を和らげる治療)を行います。
ワクチンについて
60歳以上を対象としたワクチンがありますが、RSウイルスは法令で定められた定期予防接種の対象疾患でないため、ワクチンを接種する場合は任意予防接種となります。
ジカウイルス感染症に注意しましょう
中南米地域、タイ、フィリピン、ベトナムにおいてジカウイルス感染症が流行しています。蚊が媒介するウイルスによる疾患で、基本的に人から人へ直接感染するような病気ではありません。ただし、ジカウイルスは母体から胎児への感染を起こすことがあり、小頭症などの先天性障害を起こす可能性があります。
注意
海外に流行地域へ出かける際は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊に刺されないように注意してください。
詳細については関連リンクを参考にしてください。
関連情報
動物由来の感染症について
埼玉県動物指導センターでは、動物から人に感染する「動物由来感染症」 を予防すために、動物由来感染症についてと予防についてをまとめた「動物からうつる病気があることをご存知ですか?」を同センターホームページ内にて公開しています。特に子供は、抵抗力が弱く重症化しやすいといわれていますので、ぜひご覧になり、感染予防にお役立てください。
関連情報
関連情報 リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク